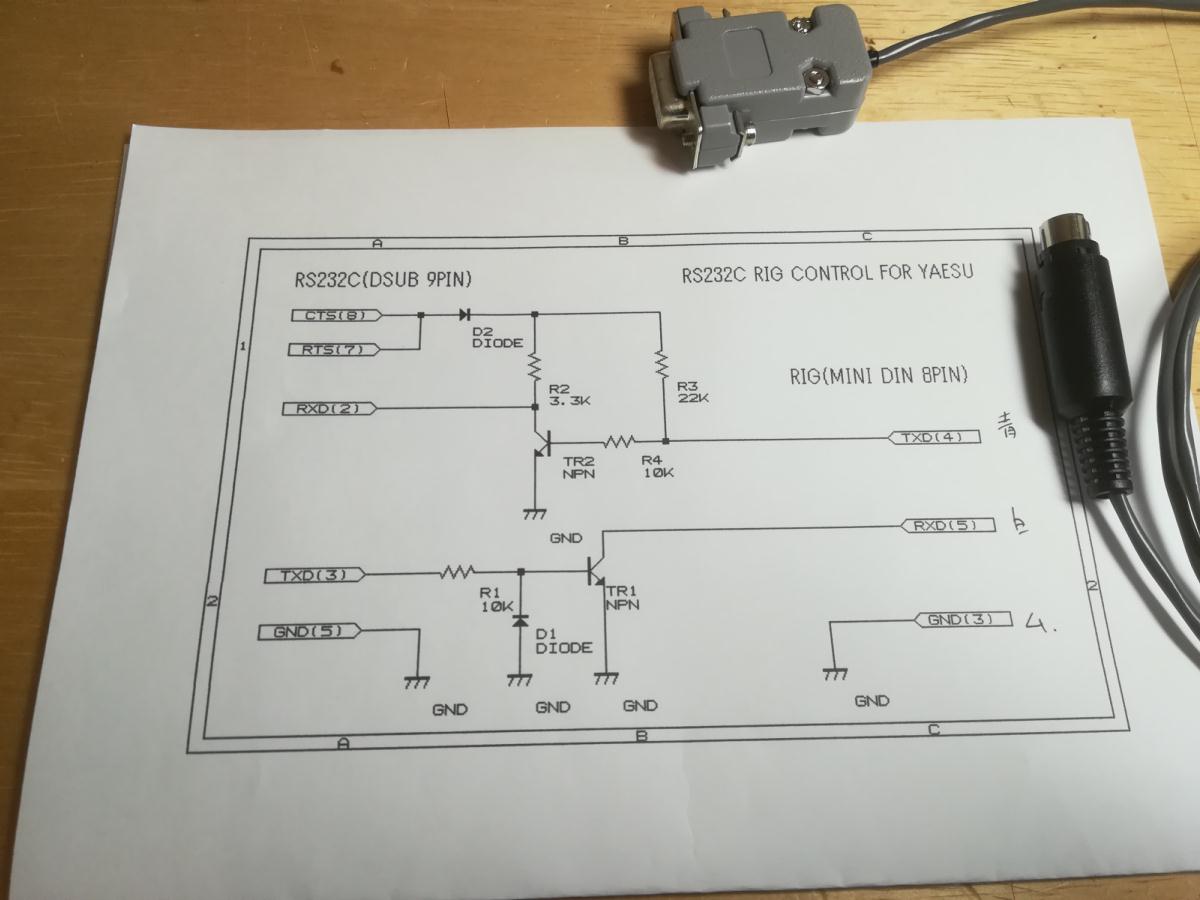作業メモ
こちらの続きで、週末に帰省して行った作業メモです。
電源操作BOXは予定通り設置し、そのままFDコンテストへ突入して完走。
PCとの連携に難ありでした。PCをシャットダウンしてもUSBへの給電は止まらず。なので、電源が入ったままになってしまいます(T_T)。BIOS設定によっては止められるものあるようですが、接続したPCでは止められず。どうやらUSBポートは止まらないようになっているようです。(USBキーボードでの電源管理とかを考えたら、そうしておかないといけませんねぇ)
#やむなくUSBを抜いて、OFFにして戻ってきた。
#手元のPCで確認しておくべきでした。
続いて、WOLが働かなくなっていた件。
やはり停電が原因。停電するとサスペンド状態が消えるんでしょうね。一度、実際に電源ボタンを押して起動し、シャットダウンした後は、WOLが使えるようになりました。(BIOSの設定が消えたわけではありませんでした)
こちらもBIOS設定で何かできないか?触りましたが、できませんでした。ネット検索していると、停電→復電したらWOLは働かなくなる、が正解のようです。WOL対象機は2台あり、主に遠隔で使いたいほうのBIOSを以下のように変更。
・AC電源をロストし、復帰したときは「起動」
としておけば、停電が起こっても、復電時に立ち上がりますので、遠隔でシャットダウン、これ以降はWOLが使えるようになります。ただ、確率は低いものの停電のあとPCが起動してしまう点が問題。起動したらmailを飛ばすなどして気が付くようにするしかなさそうです。
実家にはラズベリーパイで作った簡易NASを置いていますので、こちらのGPIOからPCの電源スイッチを操作できるようにしておくのが良いのかもしれません。(ついでにリセットもかな)
電源操作BOXは予定通り設置し、そのままFDコンテストへ突入して完走。
PCとの連携に難ありでした。PCをシャットダウンしてもUSBへの給電は止まらず。なので、電源が入ったままになってしまいます(T_T)。BIOS設定によっては止められるものあるようですが、接続したPCでは止められず。どうやらUSBポートは止まらないようになっているようです。(USBキーボードでの電源管理とかを考えたら、そうしておかないといけませんねぇ)
#やむなくUSBを抜いて、OFFにして戻ってきた。
#手元のPCで確認しておくべきでした。
続いて、WOLが働かなくなっていた件。
やはり停電が原因。停電するとサスペンド状態が消えるんでしょうね。一度、実際に電源ボタンを押して起動し、シャットダウンした後は、WOLが使えるようになりました。(BIOSの設定が消えたわけではありませんでした)
こちらもBIOS設定で何かできないか?触りましたが、できませんでした。ネット検索していると、停電→復電したらWOLは働かなくなる、が正解のようです。WOL対象機は2台あり、主に遠隔で使いたいほうのBIOSを以下のように変更。
・AC電源をロストし、復帰したときは「起動」
としておけば、停電が起こっても、復電時に立ち上がりますので、遠隔でシャットダウン、これ以降はWOLが使えるようになります。ただ、確率は低いものの停電のあとPCが起動してしまう点が問題。起動したらmailを飛ばすなどして気が付くようにするしかなさそうです。
実家にはラズベリーパイで作った簡易NASを置いていますので、こちらのGPIOからPCの電源スイッチを操作できるようにしておくのが良いのかもしれません。(ついでにリセットもかな)