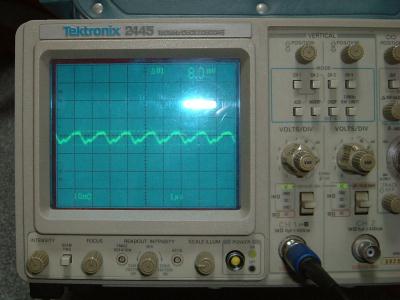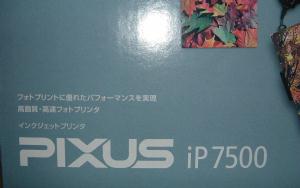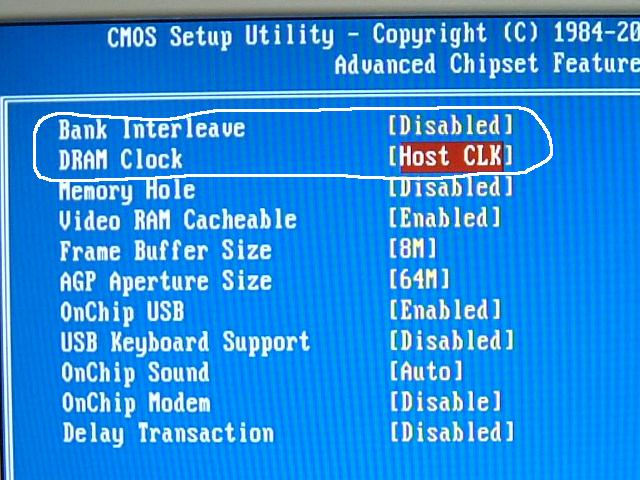すごい カード


システムトークという会社が発売している、パソコン用拡張パーツです。すごく、B級なネーミングの製品です。さて、SUGOIカードは一連のシリーズのようです。今回入手したのは、表題の写真の物。ノートパソコン用カードで、USBとLANが一つのパッケージに入った、一粒で二度美味しい(ん?)と思われる製品です。
外見やネーミングから、ジャンキーな怪しい香りを少し期待していたけど、いざ開封してみると怪しい香りはあまりない。でもよく見ると、説明書は不親切。書かれているのは手順だけ(それも不親切で舌足らず)トラブルがあった場合の対処は代表的な問題でさえ書かれていない。FAXでサポートは受けられるみたいだけど。能書きはさておき、残り少なくなった最後の怪しさが、インストールに発揮されることを密かに期待しつつ、セットアップ開始。
しかし、3分もしないウチに全部完了。
パッケージやネーミングから来るB級的な、怪しい商品といったイメージとは裏腹に普通のまともな製品でした。これで購入から丸5年経過したリブレットL1、まだまだ使えそう。USBとLANの2つが貧弱な古いノートパソコンを現役で使うには便利で、すごいカード。まさに看板に偽り無しと言ったところか。